総論
・1歳6ヶ月健診や、3歳健診で相談を受けたり、医療者側から指摘されるケースもある「言葉の遅れ」ですが、背景にはどんな原因があるのでしょうか。
・まず器質的疾患を確認し、それで問題ない場合は経過観察として定期的にかかりつけ小児科でフォローアップを行います。
器質的疾患の確認
・まず、難聴や口蓋裂の有無を確認します。
難聴
・新生児聴覚スクリーニング検査を確認します。母子手帳に結果が貼付されているので、以前難聴の指摘があったか確認できます。
・先天性サイトメガロウイルス感染症では、新生児聴覚スクリーニングで正常でも、徐々に難聴が出現してくることがある。不顕性感染症もあり見逃しの可能性もある疾患。
・滲出性中耳炎により伝音性難聴をきたすこともある。こちらも、痛みを伴わない中耳炎であり発見が遅れることがある。
・そのほか、細菌性髄膜炎やムンプスウイルス感染症、アミノグリコシド系抗菌薬やシスプラチンなどの薬剤によっても難聴をきたす可能性がある。
・健診では、簡単な聴覚テストで疑うところがあれば、耳鼻咽喉科に紹介を行う。
軟口蓋裂
・口腔内を確認、疑わしければ形成外科や口腔外科に紹介する。
ことばの発達の確認
・器質的疾患が否定できた後は、ことばの理解ができているかに注目します。
表出性言語障害
・有意語の表出が少なくとも、言葉だけの指示で理解でき、指差しで意思表示ができ、対人関係の構築ができている場合には表出性言語障害を疑う。
・この場合、三項関係の質問(例「お母さん・お父さんに〇〇してみて」)にスムーズに答えることができる。
・発達性の場合は2~3歳以降に言語発達が改善されるものがお多く、予後良好と言われている。
知的障害や自閉スペクトラム症
・ことばの遅れのみでなく、周囲に関心を示さない、視線が合わない、多動であったり模倣ができない場合、知的障害や広汎性発達障害を疑う。
・三項関係の質問に答えることは少ない。
選択制寡黙
・正常な言語能力があっても、特定の場面を除いて沈黙を保っている状態のこと。
・社会的不適応の一種であり、自閉スペクトラム症やマルトリートメントが疑われることもある。
・時期を変えて繰り返し、場慣れした状況でも発語がみられない場合には専門医紹介が望ましい。
マルトリートメント
・話す機会が極端に制限されたり話しかけられることが極端に少ないような環境や、一方向に言葉が流れる状況(テレビやDVDの視聴)が非常に多い場合、ことばの発達が遅れることがある。
・心理的な遅れ(人見知りが激しすぎたり、逆にだれにでも馴れ馴れしい感じなど)がないかも確認する。
経過観察におけるポイント
・ことばの発達は生理的範囲内でも幅があるため、診断には数ヶ月を要するため、1回の診察では判断できないことも多い。
・経過観察を行うには、保護者との良好な関係性が重要。受診を自己判断でやめてしまわないように、保育園など他施設との連携を行い、地域で見守っていく必要がある。


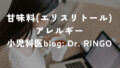
コメント