Introduction
・今回は、小児のエコー(超音波)検査に役立つポイントをまとめます。
・私が初期研修医の時含め、上級医に聞いたエコー検査のポイント、またエコー検査ワークショップで聞いた内容も含まれています!
・エコー検査における備忘録として残しておくので、適宜内容追記しアップデートする予定です。
臓器別
腎臓
・腎臓を見る時は、肝臓をエコーウインドウとして、下にある腎臓を見るようにすると良い。つまり前側から下にエコーを向ける感じ。
※エコーウインドウ:超音波が通りやすい実質臓器や液体のこと
・腎膿瘍は、腎実質内に無血管野として描出される。
腸管ガスが邪魔で見えにくい場合
→手で見たいところを押して、腸管を画面外に押し出すのがポイント
→原因になっている腸管がどこに固定されているのかをチェックすべし
→右腎臓をみたい時に上行結腸のガスが邪魔なら、外側から内側に向かって腸管を押す感じ。
肋骨が被ってしまった時のポイント
→あえて肋骨をかぶせる!という意識でも場合によっては良い
→なぜエコーをするのかがはっきりしていれば、見たいところを見れれば良い。
腎臓の出し方
<右腎臓が描出しづらい時の工夫>
→右前腋窩線から脊椎の辺りを狙う感覚でエコーを当てる。
<左腎臓が描出しづらい時の工夫>
→右と異なり肝臓のエコーウインドウがないので、前側からは腸管ガスの影響で描出が難しい。よって、気持ち後ろ側からエコーを当てると見えやすくなる。
痛がらせないエコーの持ち方
→エコーの下の方をつかんで、覆う感じでプローブを持つ。
腎臓の脈管や腎盂尿管の走行
→背側から確認する。
ドップラーをかけて、血管が正常に放射しているか見る
脾臓
・Spleenーindexが20㎠以上は脾腫
→体感的には、腎臓より大きければ脾腫の場合が多い
→赤血球見たいな形では脾腫はないこと多い。腫大してると、丸っこい感じ
・膵尾部を見るときには、脾臓をエコーウインドウにしてみるのもあり
→縦軸で背側からエコーを当てると、脾門部の右側(腹側)
肝臓
心窩部長軸から観察する場合
・SMAが出たところで、心窩部長軸での写真を残しておく。
・肝臓は大きいので、占拠性病変の見逃しをないように
・門脈はCの字で映る
心窩部横軸から観察する場合
・depthの調節、輝度の調節をして、内部の見逃しがないようにしておく。
・門脈は壁が厚い
→三つ組を構成しているので、輝度も当然高い
・下大静脈に帰るところには、門脈が3本集結している
→放射状になってる感じ
腸管
・基本はガスで見えにくい。
・ガスレスになったら、病変あるかも?と意識しておく。
・腸管は、蠕動運動を見て、動いていないところを見るのが大事
・まずは、いったん試してみて腸管エコーを覚えることが重要
卵巣・子宮
・ダグラス窩の腹水を確認。
→直腸の周囲を見る(しっかり全体をチェック)
・少量の腹水は膀胱と腸管の間にちょろっと見えることもある。
子宮はどこ?子宮の描出方法
・膀胱の下の管腔臓器を探す(体部・頸部共に1cm未満くらい)
→左右にエコーを振りながら探す必要あり
各論:傷病ごとのエコー検査方法
肘内障
・上腕骨と橈骨頭の関節を親指で押さえて、そのまま手を取って外転させる
・肘内障の場合、橈骨頭の近位にある輪状靱帯が関節腔に入り込み、J signを呈する。
・エコーは、骨折との鑑別にも役に立つ
→レントゲンがGoldーStandardではない!
→骨折では、骨折線よりも、関節内血腫でわかることもある。
頸部リンパ節腫脹
・肝脾腫ある場合、伝染性単核球症またはサイトメガロ感染症も考慮する。
・川崎病では、数珠状にリンパ節が連なって見える。
・リンパ節の確認方法としては、リンパ門(楕円形のリンパ節の中心部)に血管エコーがある場合疑わしくなる。
耳下腺
・筋肉(胸鎖乳突筋)よりも高エコー。
・顎下腺は、耳下腺よりも低エコー。
回盲部病変
・急性虫垂炎、腸重積(回腸結腸型・回腸回腸結腸型)、回盲部炎が鑑別
・多いのは、回盲部の背側(64%)
・小児の腸重積は、Targetーsignがないから否定、というよりも、回盲部病変なく正常だから否定の方が良いかも
虫垂炎
・必ず盲端まで出す!→先端だけ炎症あることもある
・GradeⅡb以上では、手術適応
→2aは血流増加、2bは血流低下、3は血流なし、腫瘤形成はやばい
・エコーで見えなければ、やはり造影CTも大事
・虫垂炎の際には、虫垂の拡張、糞石などのヒントが見えてくることも
細菌性腸炎
・上行結腸(〜横行結腸)が多い
→下降結腸の腸管浮腫があれば、ウイルス性も考えるべき
→しかし、腸重積の原因となるアデノウイルス性腸炎は回盲部にも認められる
・エルシニアとサルモネラ腸炎の鑑別
→どちらも回盲部の炎症を起こす
→エルシニアはリンパ節腫脹多い
→サルモネラはLN腫脹目立たず、上行結腸まで炎症が及んでいる
その他
・腸管の血流を見る時の注意点
→腸管外にカラーが載っていれば、アーチファクトの可能性が高い
→ゲインを下げれば見えやすくなる
エコーについての書籍紹介
・普段の診療で役立つエコー関係の書籍をまとめます!
|
|
|
|
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1796ca05.cfdb35c3.1796ca06.93e01549/?me_id=1213310&item_id=20409285&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8723%2F9784765318723_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1796ca05.cfdb35c3.1796ca06.93e01549/?me_id=1213310&item_id=20032832&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8327%2F9784765318327.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/244a79f0.d4eaac55.244a79f1.0eae1693/?me_id=1259747&item_id=15274728&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2021%2F040%2F34267986.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

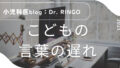
コメント