総論
・薬剤過敏症症候群(drug-induced hypersensitivity syndrome: DIHS)は、抗てんかん薬などの限られた薬剤を比較的長期間に渡り服用した後に発症する重症薬疹である。
・皮疹および肝障害といった臓器障害を繰り返し、ヒトヘルペスウイルス6型(HHV-6)などのヘルペスウイルスの再活性化を伴うことが特徴として挙げられる。
・経過中および回復後に感染症および自己免疫疾患などの合併症を発症するため、長期間の経過観察が必要と考えられている。
症状
・DIHS発症早期には、播種状紅斑丘疹といえる粟粒大から半米粒大前後の小型の丘疹、紅斑を顔面・体幹に認めることが多く、発熱・頸部リンパ節腫脹を伴う。
・顔面の浮腫性腫脹は早期から見られ、眼囲を避ける紅斑の分布が特徴的所見として挙げられる。
・皮疹は被疑薬中止3日後程度から急速に増悪することが多く、下顎や鼻周囲に小膿疱が多発するとともに痂皮を伴うようになる。
・腫脹のために開眼困難や、気道の閉塞による呼吸困難を生じることがあるため注意が必要である。
・躯幹四肢の皮疹は播種状紅斑丘疹型を認めることが多いが、多型紅斑を呈する症例も多い。いずれも拡大融合し全身性のびまん性の紅斑となり、顔面のみでなく四肢にも浮腫を認める。
・一般に下腿に紫斑を混じることが多く、DIHS重症度と紫斑面積に相関のあることが最近明らかにされている。
・粘膜疹は通常認められないが、時に口唇や口腔内の軽度をびらんを伴うことがあり、SjSとのオーバーラップとして位置づけられている。
診断基準
・高熱と臓器障害を伴う薬疹で、医薬品中止後も遷延化する。
・多くの場合、発症後2-3週間後にHHV-6の再活性化を生じる。
・以下の主要所見を満たす場合、DIHSの診断となる。
主要所見
1. 限られた医薬品投与後に遅発性に生じ、急速に拡大する紅斑、しばしば紅皮症に移行する
2.原因医薬品中止後も2週間以上遷延する
3.38℃以上の発熱
4.肝機能障害
5. 血液学的異常:a, b, cのうち1つ以上
a. 白血球増多(11,000/mm³以上)
b. 異型リンパ球の出現(5%以上)
c. 好酸球増多(1,500/mm³以上)
6.リンパ節腫脹
7.HHV-6の再活性化
典型的DIHS:1-7すべて
非典型的DIHS:1-5すべて
※ただし、4に関してはその他の重篤な臓器障害をもって代えることができる
参考所見
1.原因医薬品は、抗てんかん薬、ジアフェニルスルホン、サラゾスルファピリジン、アロプリノール、ミノサイクリン、メキシレチンであることが多く、発症までの内服期間は2-6週が多い。
2.皮疹は初期は紅斑丘疹型で、のちに紅皮症に移行することがある。顔面の浮腫、口囲の紅色丘疹、膿疱、小水疱、鱗屑は特徴的である。粘膜には発赤、点状紫斑、軽度のびらんが見られることがある。
3.臨床症状の再燃がしばしば見られる。
4.HHV-6の再活性化は、
1.ペア血清でHHV-6 DNAの検出
2.血清(血漿)中のHHV-6 DNAの検出
3.末梢血単核球あるいは全血中の明らかなHHV-6DNAの増加のいずれかにより判断する。ペア血清は発症後14日以内と28日以降(21日以降で可能な場合も多い)の2点で確認するのが確実。
5.HHV-6以外に、サイトメガロウイルス、HHV-7、EBウイルスの再活性化も認められる。
6.多臓器障害として、腎障害、糖尿病、脳炎、肺炎、甲状腺炎、心筋炎も生じ得る。
検査
血液検査
・末梢血検査では、好酸球数と異型リンパ球数についての確認を行う。5%以上の異型リンパ球の出現と1500/mm³以上の好酸球数増多はDIHSの診断基準にも含まれる重要な項目である。
・血清TARCは高値を示し、診断バイオマーカーとして有用。
・特徴的な検査所見は、発症後3週前後で見られる、ヒトヘルペスウイルス(HHV)-6の再活性化。抗HHV-6の再活性化がみられるため、抗HHV-6 IgG抗体価を初診時(発症14日以内)と2-4週後に測定し、ペア血清の4倍以上の上昇をもって再活性化と判断する。または、血清中あるいは全血中のHHV-6のウイルスDNAを測定する。
・腎障害(Cre 1.0 mg/dL以上)、肝障害(ALT400IU/L以上)、CRP高値(10mg/dL以上)などは発症早期から見られることが多い。
・また、HHV-6以外にもHHV-7、EBV、サイトメガロウイルス(CMV)の再活性化を生じるが、特にHHV-6の後に再活性化するCMVは消化管出血、肺炎、腹膜炎などの重篤な症状を誘発し致死的な経過をたどることもあるため、慎重なフォローアップが必要である。
・CMV再活性化発症時期に一致して、血小板数の減少や肝障害の増悪が見られる事が多く、発症早期での検査値の確認に注意する。
・DIHSでは肝胆道系酵素の上昇を認めるが、いったん改善した後も数ヶ月にわたり再燃を繰り返すことがあるため継続的なフォローアップが必要である。
治療
基本的な考え方
・治療の基本は原因薬の中止+入院加療。
・特に薬剤中止数日後から発熱、リンパ節腫脹および顔面の腫脹をはじめとする皮疹の急激な悪化が見られることがあるので、患者にも伝えておく。
・重症度スコア(DDSスコア)を参照に、軽症例では保存的に、重症例では積極的な治療を行う。
ステロイド薬全身投与
・重症度が中等症から重症では、PSL1mg/kg/dayを目安に開始する。
・一般的には、1~2週の投与後に、皮膚所見、血液検査データを参考にしながら5-10mg/日ずつ減量する。
・減量中には再結成化による合併症を生じやすいため、慎重に減量する。
ステロイドパルス療法
・安易に開始すべき治療ではないが、要する場合は行う。
・合併症として自己免疫疾患発症のリスクがある。
免疫グロブリン大量静注療法
・ステロイドパルスとどうよに、その効果に対しては一定の見解が得られていない。
抗サイトメガロウイルス療法
・DIHS発症1ヶ月〜1.5ヶ月前後にしばしばCMV再活性化を認め、時に肺炎、消化管出血、心筋炎、腎障害などのCMV病を発症する。
・抗ウイルス薬(ガンシクロビル)を投与し、CMV抗原血症が陰性化するまで治療を継続投与する。

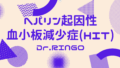

コメント