今回は抗てんかん薬についてのまとめです。
てんかん自体については、以前の記事でまとめてます。
治療のポイント
・2回以上の発作で治療を開始し、発作型分類を念頭に、症候群診断、長期的予後を推定し、副作用、患児の年齢と性別、併存症に配慮した薬剤選択をします。
・薬剤の副作用として、増量に伴い徐々に出現する眠気、ふらつきや、検査でのみ分かる血液検査異常よりも、特異的副作用である発疹、保護者との信頼関係を損ないやすい発作増悪に特に注意する。
・潜在する副作用として、長期に及ぶ影響から催奇形性、知的発達・認知行動への副作用にも注意することが必要。
投与量の調節
・選択するべき薬剤が決定したら、治療域下限の半分程度から開始する。
・副作用を避けるために、1-2週ごとに薬剤に応じた増量幅で漸増する。
・基本的には必要最低限の投与量が望ましい。再発がなければ治療域下限のまま継続。
・概ね治療前の発作間隔の3倍の期間発作が抑制できれば有効と判断する(3の法則)
血中濃度の測定
・怠薬と副作用の有無を確認するため、初期は3-6ヶ月、2年以上発作が抑制できれば6-12ヶ月程度の間隔で薬物血中濃度、血液生化学検査、検尿などを行う。
主な副作用
治療開始直後
・眠気、ふらつき、焦燥感、イライラ感、聴覚障害(カルバマゼピン)
開始後2-3週
・発疹などの過敏症、重症薬疹
長期使用中
・肝機能障害、膵炎(バルプロ酸)、発汗障害・尿路結石(ゾニサミド、トピラマート)、歯肉肥厚・多毛(フェニトイン), 葉酸や骨代謝の障害
全般発作の治療薬
・生涯の内服を想定し、催奇形性のリスク回避のため性別によって薬剤選択も変わってくる。
全般性強直間代発作
男性の場合
①バルプロ酸(デパケン、セレニカ、バレリン)
用量:10-30 mg/kg/日 分2-3
調節:発作抑制が得られるまで10 mg/kg/日 増量可(1週間程度の間隔毎)、最大量40mg/kg/日
血中濃度:40-100 μg/mLを目安に増量。成人では1日量最大1200mg
副作用:血小板減少、高アンモニア血症、急性膵炎、ファンコー二症候群、食欲亢進、低カルニチン
注意点:カルバペネム系抗菌薬(メロペネム、パニペネムなど)との併用は禁忌。蛋白結合率の競合や肝臓でのグルクロン酸抱合代謝亢進により、VPA血中濃度が大幅に低下する可能性がある。
②レベチラセタム(イーケプラ)
用量:20mg/kg/日 分2
調節:発作抑制が得られるまで増量幅として20mg/kg/日以下の範囲で2週間以上の間隔で、最大60mg/kg/日まで増量可能。ただし50kg以上の小児では、成人と同様に増量幅1000mg、1日最大量3000mg
③ゾニサミド(エクセグラン)
用量:2mg/kg/日 分2-3
調節:発作抑制が得られるまで、増量幅として2mg/kg/日以下の範囲で、1週間以上の間隔で最大12mg/kg/日まで増量可能
④ラモトリギン(ラミクタール)
単剤療法の場合
用量: 最初の2週間 0.6mg/kg/日 分1-2
調節:増量幅として0.6mg/kg/日 以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて、200mg/日まで増量できる。
バルプロ酸併用の場合
用量: 最初の2週間 0.15mg/kg/日、次の2週間 0.3mg/kg/日 分1
調節: 0.3mg/kg/日以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて増量。
バルプロ酸の他にグルクロン酸抱合を誘導する薬剤(フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤)を併用している場合
5mg/kg/日(200mg/bodyが上限)まで増量可能。
グルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用していない場合
3mg/kg/日(200mg/bodyが上限)まで増量可能
バルプロ酸を併用していない場合
①グルクロン酸抱合を誘導する薬剤併用時
用量:最初の2週間は0.6mg/kg/日、次の2週間 1.2mg/kg/日 分2
調節:1.2mg/kg/日 以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて、15mg/kgまで。最大量400mg/日まで増量可能
② ①以外の薬剤併用時は、バルプロ酸併用時と同じ。
女性の場合
第一選択薬としては、上記の②以下、つまりバルプロ酸以外を選択。
バルプロ酸は他の薬で発作抑制が困難な場合に最少量での使用とする。
欠神発作
エトスクシミド(ザロンチン、レピレオプチマル)
用量:10-15mg/kg/日 分2
調節:発作抑制が得られるまで 5-10mg/kg/日。1-2週間の間隔で、最大量30mg/kg/日
血中濃度:40-100μg/mLを目安として増量。ただし成人では最大1000mg/日
ミオクロニー発作
レベチラセタム(イーケプラ): 上記に同様
焦点発作の治療薬
下記のいずれかを選択
レベチラセタム(イーケプラ)
適応:4歳以上の部分てんかん、強直間代発作
用量:10-20 mg/kg/日で開始 →4歳以上:20-60 mg/kg/日
【調節】
・発作抑制が得られるまで増量幅として20mg/kg/日以下の範囲で2週間以上の間隔で、最大60mg/kg/日まで増量可能。
・ただし50kg以上の小児では、成人と同様に増量幅1000mg、1日最大量3000mg
ゾニサミド(エクセグラン)
用量:2mg/kg/日 分2-3
調節:発作抑制が得られるまで、増量幅として2mg/kg/日以下の範囲で、1週間以上の間隔で最大12mg/kg/日まで増量可能
ラモトリギン(ラミクタール)
単剤療法の場合
用量: 最初の2週間 0.6mg/kg/日 分1-2
調節:増量幅として0.6mg/kg/日 以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて、200mg/日まで増量できる。
バルプロ酸併用の場合
用量: 最初の2週間 0.15mg/kg/日、次の2週間 0.3mg/kg/日 分1
調節: 0.3mg/kg/日以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて増量。
バルプロ酸の他にグルクロン酸抱合を誘導する薬剤(フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、プリミドン、リファンピシン、ロピナビル・リトナビル配合剤)を併用している場合
5mg/kg/日(200mg/bodyが上限)まで増量可能。
グルクロン酸抱合を誘導する薬剤を併用していない場合
3mg/kg/日(200mg/bodyが上限)まで増量可能
バルプロ酸を併用していない場合
①グルクロン酸抱合を誘導する薬剤併用時
用量:最初の2週間は0.6mg/kg/日、次の2週間 1.2mg/kg/日 分2
調節:1.2mg/kg/日 以下の範囲で1週間以上の間隔をあけて、15mg/kgまで。最大量400mg/日まで増量可能
② ①以外の薬剤併用時は、バルプロ酸併用時と同じ。
ラコサミド(ビムパット®︎)
適応:4歳以上の部分発作(二次性全般化を含む)
用量:2mg/kg/日 分2 から開始。
体重30kg未満の小児:2-6 mg/kg/日(最大12mg/kg)
体重30-50kg:2-4 mg/kg/日(最大8mg/kg)
50kg以上の小児:成人同様に最大400mg/日
調節:発作抑制が得られるまで、2mg/kg/日以下の範囲で1週間以上の間隔で増量。
ex) 2mg/kg/日 2週間→3mg/kg/日 2週間→4mg/kg/日
有効血中濃度
・てんかん診療ガイドラインより、血中濃度測定の有用性はA~Dに定められている。
A:非常に有用
ラモトリギン(ラミクタール®️) 2.5-15 μg/mL
フェニトイン(アレビアチン®️、ヒダントール®️) 7-20
B:有用
カルバマゼピン(テグレトール®️) 4-12 μg/mL
バルプロ酸ナトリウム(デパケン®️、セレニカ®️) 50-100
ペランパネル水和物(フィコンパ®️) 0.05-0.4
フェノバルビタール(フェノバール®︎、ルピアール®️、ノーベルバール®️) 15-40
ルフィナミド(イノベロン®️) 30-40
C:ある程度有用
エトスクシミド(エピレオプチマル®️、ザロンチン®️) 40-100μg/mL
ゾニサミド(エクセグラン®️) 10-40
トピラマート(トピナ®️) 5-20
プリミドン(プリミドン®️) 5-12
D:限定的または未確定
上記以外の抗てんかん薬
治療の変更
・第一選択薬が無効の場合、または副作用の出現時は第二選択薬を開始し、第一選択薬を減量する。
・重症副作用が出た場合は即時第一選択薬を中止。
治療の中止、成人期
・2-3年の発作抑制後、減量を試み治療終了を目指す。子供の成長発達に応じて、治療方針の決定を親だけでなく患者本人とも相談できるようにしていく。
・発作が抑制されていても、成人期まで内服治療を必要とするケースも多い。自動車運転免許、妊娠、就労などへの影響についても、本人と相談のもと考慮が必要となる。



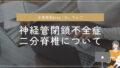
コメント