PFASとは
・花粉-食物アレルギー症候群:PFAS(Pollen-Food Allergy Syndrome)は、花粉症と果物アレルギーの両方の症状を引き起こすアレルギーのことです。
・花粉症の症状としては、鼻水や目のかゆみ、くしゃみなどがあります。
・果物アレルギーの症状としては、口や喉のかゆみ、腫れ、発疹、胃腸の不快感などがあります。
・ある特定の花粉抗原にIgE感作されると、交差抗原性のある植物性食物を摂取した時にアレルギー症状をきたします
・PFASでは、原因食物を摂取した直後に始まる口腔咽頭症状が主兆となるため、口腔アレルギー症候群(OAS: oral allergy syndrome)の臨床病型を示すことが多いです。
・OASの定義には、花粉症の既往や原因食物を植物性食品に限定する記載は含まれていません。
発症機序
・花粉抗原と植物性食物抗原の間の交差反応に起因します。
・果物や野菜、豆類、稀にスパイスなどが原因食品となります。
・花粉に感作された患者の口腔粘膜に食品が接触することで症状がはじまりますが、嚥下された後はアレルゲンエピトープが消化過程で消失しやすいため、それ以外の症状が出ることは少ないです。
・主な原因アレルゲンは、Bet v 1ホモログ(別名:pathogenesis-related protein: PR-10)やプロフィリンなどのプロテインファミリーに属します。
・Bet v 1ホモログの感作源はカバノキ科樹木の花粉(シラカンバ、ハンノキ、オオバヤシャブシなど)のみです。
・一方プロフィリンは、カバノキ科樹木からイネ科(カモガヤ、オオアワガエリなど)、キク科(ブタクサ、ヨモギなど)の雑草まで多種の花粉が感作源になる可能性が報告されています。
・また最近、ヒノキ花粉由来ジベレリン制御蛋白(gibberellin-regulated pretein: GRP)に感作されて、モモなどのPFASが生じ得るとの報告もあります。
花粉と植物性食品の関係
カバノキ科
交差反応に関与する主なプロテインファミリー:Bet v 1ホモログ(PR-10)、プロフィリン
カバノキ科樹木の花粉:シラカンバ、ハンノキ、オオバヤシャブシなど
交差反応のある食物
バラ科(リンゴ、モモ、サクランボ、ナシ、アンズ、アーモンド)
マメ科(大豆、ピーナッツ、緑豆もやし):大豆には交叉性のあるPR-10であるGly m 4が含まれている。加熱や発酵などの加工処置で活性を失いやすいという性質があり、豆腐や味噌・納豆などの摂取では症状を認めないが、豆乳摂取時のみ症状を呈することあり。
マタタビ科(キウイフルーツ)
カバノキ科(ヘーゼルナッツ)など
ヒノキ科
交差反応に関与する主なプロテインファミリー:Polygalacuturonase
交差反応のある食物
ナス科(トマト)
イネ科
交差反応に関与する主なプロテインファミリー:プロフィリン
イネ科:カモガヤ、オオアワガエリなど
交差反応のある食物
ウリ科(メロン、スイカ)
ナス科(トマト)
マタタビ科(キウイフルーツ)
ミカン科(オレンジ)
マメ科(ピーナッツ)など
キク科
交差反応に関与する主なプロテインファミリー:プロフィリン
キク科:ブタクサ、ヨモギなど
交差反応のある食物
ブタクサ属:ウリ科(メロン、スイカ、ズッキーニ、キュウリ)、バショウ科(バナナ)
ヨモギ属:セリ科(セロリ、ニンジン、スパイス類:クミン、コリアンダー、フェンネルなど)、ウルシ科(マンゴー)など
疫学
・全国の小中学校を対象にした質問紙による調査では、バラ科果物や大豆によるPFASの有病率は小学校で0.99%、中学校で2.75%で、モモが原因として多かった。
・2021年の日本での出生コホートによる質問紙による調査では、13歳時のPFASの有病率は11.7%で、原因食物としてキウイフルーツとパイナップルが最多だった
症状
・原因食物を摂取した直後から1時間以内に、口唇や舌、口腔咽頭粘膜のかゆみや刺激感(イガイガ、チクチク)を自覚する。
・口唇や口腔粘膜の腫脹、水疱や血疱などの他覚的所見を認めることもある
・時に、引き続いて鼻症状(鼻腔の痒み、くしゃみ、鼻汁、鼻閉)、眼症状(流涙、眼球結膜の充血や浮腫)、耳症状(耳孔のかゆみ)、皮膚症状(眼瞼や顔面の浮腫、全身性蕁麻疹)、消化器症状(腹痛、嘔気嘔吐、下痢)、呼吸器症状(呼吸困難、喘鳴、喉頭浮腫)があらあわれ、アナフィラキシーショックに陥ることもある
・PFASでは口腔咽頭症状に限局する軽症例が多いが、カバノキ科花粉-豆乳の間の交差反応や、ヨモギ花粉-スパイス(セリ科のセロリ、にんじんやスパイス)の間の交差反応ではアナフィラキシーに進展しやすい点には注意
検査
・皮膚プリックテストでの検査が一般的。
・原因食物のアレルゲンエピトープの脆弱性から、標準化された抗原液を用いると偽陰性になりやすい点に注意。そのため、新鮮な食品を使ったprick-to-prick testが有用である。
・一方、感作花粉の特定には特異的IgE抗体を測定する。
・負荷試験を行う場合、新鮮な果物切片を数分間口に含ませた後に吐き出す「口含み試験」、あるいは舌下に接触させてから取り出し、その後の口腔症状の出現を観察する「舌下投与試験」などがある
治療
PFASの治療は、抗ヒスタミン薬やステロイド薬などの薬物療法が主な方法です。また、果物を加熱することで、アレルギー反応を軽減することができます。ただし、加熱によってアレルギー反応が軽減されない場合もあります。
・軽微な症状であれば、少量の摂取に限り許可しても良いですが、アナフィラキシーの既往がある場合や、重篤な症状を誘発しうる食品(豆乳、スパイスなど)については厳しく制限します。
以上がPFAS(花粉-果物アレルギー)についてのまとめです。花粉症と果物アレルギーの両方の症状がある場合は、PFASの可能性があるので、アレルギー科で診断を受けることをおすすめします。
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1796ca05.cfdb35c3.1796ca06.93e01549/?me_id=1213310&item_id=20529085&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2083%2F9784877942083_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

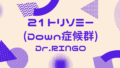
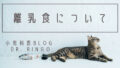
コメント