総論
・小児脳腫瘍や小児がんの中では白血病に次いで多く、小児がんの20%を占めており、実質臓器に発生する固形腫瘍のなかでは最多。
・脳腫瘍は発生部位により鑑別を絞ることができる。
・小児では造影効果の多寡が悪性度を反映しないことがある。
・2021年に、「脳腫瘍WHO分類(第5版)」が改定されており、テント上に発生する小児脳腫瘍で新たに追加された疾患が複数存在する。
・以前、脳腫瘍について総論でまとめたblog記事は下記参照
発生部位と鑑別
大脳
・glioma
・glioneuronal tumor
・embryonal tumor
・ependymal tumor
松果体
・松果体芽腫
・胚細胞性腫瘍
・網膜芽細胞腫
脳幹
・diffuse midline glioma
後頭蓋窩
・髄芽腫
・上衣腫
・脈絡叢腫瘍
眼球〜視神経
・網膜芽細胞腫
・毛様細胞性星細胞腫
下垂体
・胚細胞腫瘍
・LCH
・頭蓋咽頭腫
・下垂体芽腫
小脳
・dysplastic cerebellar gangliocytoma(Lhermitte Duclos disease)
神経膠腫
・WHO分類第5版ではgliomaはdiffuse typeとcircumscribed typeに分類され、diffuse typeにpediatric-type diffuse low-grade glioma(pLGG)と、pediatric-type diffuse high-grade glioma(pHGG)が新たに分類された。
pLGG/pHGG
pLGG
・diffuse astrocytoma, MYB- or MYBL1-altered
・aangiocentric glioma
・polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young(PLNTY)
pHGG
・diffuse midline glioma, H3 K27-alterd
・diffuse hemispheric glioma, H3 G34-mutant
・diffuse paediatric-type high-grade glioma, H3-wildtype and IDH-wildtype
・infant-type hemispheric glioma
・pLGG, pHGGは両者とも分子学的・遺伝子学的な探索により診断されるものであり、pLGGではRAS/MAPK pathway, pHGGではヒストン(H3)の変異により発生し、成人の悪性神経膠腫でみられるIDHや1p/19q co-deletionの変異は認めない。
・pLGGはいずれもけいれん発症が多く、皮質〜皮質下に及ぶT2強調像。FLAIR像の高信号を呈する
・PLNTY(polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young)では粗大な石灰化や嚢胞を伴うことが特徴的。
diffuse midline glioma, H3 K27-altered(WHO CNS grade4)
・小児のびまん性内在性橋神経膠腫とよばれていた腫瘍の多くにヒストンタンパク質であるH3 K27の変異があることが判明しており、悪性度が高く、2年生存率は10%以下と非常に低い。
・小児では脳幹部(主に橋)の発生が多いが、20歳以上では視床や脊髄にも発生する。
・脳幹を中心とした浸潤性の増殖を示し、拡散制限はないか軽度であり、造影効果は多彩。部分的に造影される場合や、造影効果に乏しい場合もあるため、悪性度の推定が画像では難しい。
・播種を伴うことも多い(約25%)
※ヒストン:染色体を構成する主要なタンパク質であり、H2A, H2B, H3, H4の4種類が八量体を形成してDNAに結合しており、DNA領域の転写調節に重要な役割を担っている。
circumscribed astrocytic gliomas: pilocytic astrocytoma(WHO CNS grade1)
・WHO第5版で追加された。
・pilocytic asatrocytoma(PA)は、若年者の小脳や視床下部(視神経、視交叉、第3脳室近傍)に好発し、神経線維腫症1型(neurofibromatosis; NF-1)に伴う視神経膠腫に代表されるが、NF-1の合併がなく発生することもある。嚢胞性成分と充実性成分が混在した境界明瞭な腫瘤を呈することが多く、石灰化もしばしば伴う。
・充実性成分は脳実質と比べてT2強調像で高信号を呈し、ADC値は悪性神経膠腫に比べて高く、強く造影されることが多いが、ASL法によるCBF値が低値を示す。
・類似する腫瘍が乳幼児に発生した場合はPAのsubtypeであるpilomyxoid astrocytoma(毛様類粘液性星細胞腫)の可能性もあり、PARTと比べて予後が悪いことが知られている。
tumors of sellar region and pineal tumors
頭蓋咽頭腫(CNS WHO grade1)
・頭蓋咽頭腫に沿って遺残した扁平上皮から発生する良性腫瘍。
・小児に発生するエネメル上皮腫型(adamantinomatous craniopharyngioma)と、中年に発生する乳頭型頭蓋咽頭腫(papillary craniopharyngioma)があり、第5版からは異なる腫瘍であることが示唆された
・エナメル上皮腫型は鞍上部を中心に存在する分葉状の嚢胞性腫瘤であり、増強される壁在結節と結節状あるいは環状の石灰化が特徴である。
・鑑別にはRathke嚢胞や出血/嚢胞変性を伴った下垂体腺腫が挙げられるが、石灰化を同定することが診断に有用である。
胚細胞性腫瘍(germ cell tumor; GCT)
・治療反応性のよい胚腫(germinoma)と、反応性が悪い非胚腫(non-germinomatous germ cell tumor)、これらの混合腫瘍(mixed GCT)からなる胚細胞由来の腫瘍であり、10歳代に好発する。
・約50%が松果体部、20-30%は鞍上部に認められ、5-10%では両方に生じる(いわゆるbifocal germinoma)
・その他、基底核や視床、脳幹、脊髄にも発生する。松果体部では男女比10:1と男性に多いが、鞍上部では性差はない。
・単純CTでは脳実質と比べて軽度高吸収を示し、高い細胞密度を反映した所見である。内部に多数の嚢胞を伴うことがあり、充実性成分には明瞭な造影強調効果を認める。
・内部に出血や脂肪を認めた場合には, mixed GCTを考慮する。
・髄膜播種をきたすことも多いため、脳・全脊椎の播種検索は必須であり、10年以上経過して再発することもある。
・腫瘍マーカーとしては胎盤型アルカリフォスファターゼ(PLAP: placentalalkaline phosphatase), AFP, hCGの測定も診断に有効
松果体芽腫瘍(CNS WHO grade4)
・松果体細胞腫、中間型松果体細胞腫、松果体芽腫に分類される。
・松果体芽腫はmicro RNA変異、MYC/FOXR2活性化、RB1変異(網膜芽細胞腫合併)のsubtypeにより播種の頻度や予後が大きく異なる。
・画像所見がgerminomaと類似する点が多いが、石灰化の形態が鑑別のポイントであり、germinomaは松果体の生理的石灰化を内部に抱き込むような形態(engulfed calcification)である一方、松果体実質腫瘍では石灰化を散在性に散らばせたような形態(exploded calcification)を呈すると言われている。


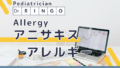

コメント